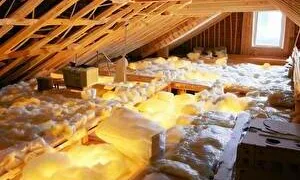もうずいぶんと、放置していたウッドフェンスの腐食した支柱。
見るたびに気にはしてはいましたが、まだ、フェンスがぐらつくような状態にはなっていなかったので、そのままにしていました。
ほぞ接ぎの加工技術には不安はありますが、まもなく迎える台風シーズンに入る前に、修理に挑戦することにしました。
ウッドフェンスのメンテナンス、手入れ次第で木製フェンスも長持ち
木製品を屋外で使用すると腐食が心配
木製品は温かみがあり、自然を感じられるので癒し効果もあるのではないでしょうか。その反面、維持管理に労力が必要となります。特に屋外に設置した木製品においては、腐食は最大の敵となることでしょう。
木材の腐食の原因は木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん)で、水気があると腐朽菌を生息させてしまいます。ですから、しっかりと木を乾燥させることで木材腐朽菌は生息できなくなり、木材の腐食を防ぐことができます。
木製品の防虫・防腐塗料
私は、ウッドフェンスの制作当時から防虫・防腐塗料を毎年塗布して管理しています。もちろん、しっかりと乾燥させた木材を使ってウッドフェンスを作っています。
私がいつも使っている、防虫・防腐塗料

フェンス支柱の腐食は木材腐朽菌?それともシロアリ?
ウッドフェンスは腐食に比較的強いヒノキを使用しています。(ネットの写真と比べると、シロアリ被害のようにも見えます。)そして毎年ウッドフェンスのメンテナンスとして水性の防虫・防腐塗料を塗っていますが、それでも雨の影響をうけますので、やはり水気が溜まりやすい支柱下部は腐りやすい部位といえます。
表面を剥がすと、かなり腐食がすすでいる

腐食が進んだフェンス支柱
ウッドフェンスには10本の支柱を使用していますが、このような状態は1本だけですから同じ条件で、この支柱だけ木材腐朽菌で腐食するとは考えにくいため、シロアリが原因のように思います。いずれにせよ腐食部分を除去しなくてはいけません。
シロアリの被害のように見えます

腐食した支柱は部分的に交換できる。
もしも、ウッドフェンスの支柱に腐食が発生した場合は、次のような対処法が考えられます。
対処法1 腐った支柱を交換する
ウッドフェンスの組立て方法にもよりますが、一番確実なのは支柱下部が腐食した支柱を新しく交換する。
メリット
・支柱を新しくすると、強度の面で一番信頼できる。
・取付け部品は意外と多いかも知れませんが、分解して柱を交換する方法は、それほど高い加工技術を必要としない。
・電動工具を使うとビスの取り外し、取り付けは意外と短時間で終了できる。
デメリット
・支柱の材料を購入する必要がある。
・同じ材料が手に入らない場合がある。
・材料の購入費用がかかる。
対処法2 支柱の腐食部分だけを交換する。【解体なし】
ウッドフェンスの解体をせずに、そのままの状態で支柱の下部だけを交換します。この方法は技術的にかなり難易度が高いように思います。
メリット
・解体不要なため、腐食部分の取り外しまでは、短時間で作業できる。
・ウッドフェンスを作った時の端材を使用しているため、材料費は0円
・端材は当時にペンキを塗っているので、色合いに違和感がない。
デメリット
・作業の難易度が高い。
・作業計画の段階では、支柱をジグソーで切る予定でしたが、ジグソーで切るには厚みがあり過ぎのため、使用できず。
・高さの調整をして、隙間なく組み立てるのはかなり困難。
・腐食部分を除去して、その後の作業時間が大変長くなります。
・浮いている支柱を加工するとき、ノコギリで支柱を下から上向きに切る作業では、ノコギリをうまく使えなく、まっすぐに切れない。
対処法3 支柱の腐食部分だけを交換する。【解体、組み立て】
この方法は、記事の執筆中に思いついた方法です。腐食部分をほぞ接ぎにて交換することを前提で考えると、対処法2では十分な作業姿勢をとれないことから、ただでさえ難しいほぞ接ぎ作業をさらに難しくしている。
その解決方法として、腐食している支柱を一旦解体して取り外してから、ほぞ接ぎ作業をした方が作業がしやすくなります。ほぞ接ぎでは少し長めにしておいて、最後に支柱をカットして支柱の高さの調整を行うほうが良いようです。
メリット
・ほぞ接ぎの作業をしやすくなる。
・ほぞ接ぎ後に柱をカットして高さを調整できるので、仕上がり良い。
デメリット
・解体作業を必要とする。
・組み立て作業を必要とする。
木材建築では古くから行われている技法を参考
今回のDIYによるウッドフェンスの修理では、支柱の部分交換を選択しています。その際、日本の伝統建築技術である、「根接ぎ」という技法を参考にしています。
出典:建築用語集 より要約
”根接ぎ”とは柱の下の部分が腐食したりしたとき、柱全体を入れ替えしないで、腐食した部分だけを新しい柱に交換すること。
出典: 京町屋用語集
代表的な根接ぎは金輪接ぎ、追っかけ大栓、台持ち、腰掛鎌など
「二方胴付き」ほぞ接ぎを選んだ理由とは
今回、接ぎの中で一番シンプルな 「二方胴付き」 というほぞ接ぎをもちいて、腐食した支柱を修理してみました。本来であれば根接ぎで用いられるような、しっかりした接ぎが柱の修理に適しているのでしょうが、あまりに高度な技術が必要なため、私には出来そうもありません。
また、フェンスの場合、横から風を受けて支柱を曲げるような力が働きますので、対処法1で紹介したように新品の支柱に交換するのが望ましいのです。もしも、風の通り道であるウッドフェンス一番左端の支柱が腐食していれば、支柱を新しく交換していたと思います。
幸い、我が家のウッドフェンスは隣家のすぐ裏にあり、腐食した部分は風が一番当たりにくい場所であることから、ほぞ継ぎによる修理を選択しました。
金輪接ぎは高度な技術が必要
本来、金輪接ぎなどを用いた根継ぎとは、建物の柱の下端近くが腐食した際に柱の下部を一部を交換することです。
金輪接ぎなどで十分な強度を得るには高い技術が必要ですので、一般のかたには不向きです。
「対処法1 支柱を新しいものに交換」をおすすめする根拠
地震や強風の際、家屋の柱には曲げる力も加わりますが、通常、柱にかかる外力は殆どが圧縮力だと考えて問題ないと思います。
それに比べて、ウッドフェンスのように軽量で風にさられる構造物では、支柱に加わる外力は殆どが曲げる力であると思われます。そのことから、安全面を考えたら ”対処法1の支柱の交換” を一番おすすめします。
DIYによるウッドフェンス支柱の修理例のご紹介
作業を始める前に準備品するもの
ノコギリ、金槌、ノミ、インパクトドライバー、充電ドライバーと木工ドリル
使用した道具

腐食したウッドフェンス支柱を切断
今回は二方胴付きホゾ接ぎによる支柱の補修を行いますので、腐食が及んでいない部分でホゾ接ぎの加工を行います。
ほぞ加工用のケガキ
残す支柱は空中に浮くような状態でホゾ部の加工をおこなうため、加工しやすい凸形状としています。新しく交換する支柱下部には凹形状の加工を行います。
交換する支柱に二方胴付きホゾのケガキ線

ホゾ接ぎのケガキ線でカット
固定用金具は再利用しますので、ボルトナットを外し腐食木材を取り除きます。
腐食した支柱を切断

支柱にほぞを加工
この写真は一回目にノコで下から縦引きして切って作ったほぞです。しかし、細くなりすぎたので柱が短くはなりますがもう一度ホゾの加工をやり直しています。
ノコで切り出して細くなったホゾ

二回目のほぞ加工ではノミを使って削り出しましたが、ノミにより平面を削り出すのはたいへん難しいものです。やはり、切り口の仕上がりではノコにかないません。
かと言って、この状態では上手くノコを引けませんので、やはりウッドフェンスの一部を解体し、この支柱を取り外してからほぞ加工を行うことをおススメします。
部分交換する支柱の加工
ウッドフェンスを製作するときに余っていた角材を使用して支柱の修理を行います。
ほぞの溝加工
ほぞの一番奥の部分は木工ドリルを使うと加工が楽です。ちなみに、下の写真は2回目です。一回目に穴を2個あけたのですが、木の繊維にドリルを流されてケガキからはみ出してしまいました。
ボール盤をご使用になれば、まっすぐに穴を開けることはできると思いますが、ハンドドリルではあまりケガキの際を狙わないほうが良いようです。ちなみに下の写真の裏側はケガキのかなり内側を貫通しています。
ドリルを使ってほぞ加工

ノミを使ってホゾを削り出し
ドリルで穴を開けた後に両サイドのケガキに沿ってのこで切り込み、その後のみで少しづつ削り出していきます。ほぞは嵌めあいをあまり緩くしたくありませんので、当て木をしてハンマーで叩き入れていきます。
ノミを使って削り出し

部分交換する柱の高さ調整
下の写真はどれだけ支柱の交換部品を切断するかを調べているところです。ほぞ加工した交換部品を台座の金具に仮組して、フェンスに残っている支柱と重なり合っている長さだけ交換部品の下端(仮組している金具の中側)をカットしてから組み立てます。
部分交換する柱のカット寸法を計測

支柱のほぞ接ぎ完了
ホゾ接ぎ部はゴムハンマーで叩いて繋いでいます。
ホゾ接ぎ完了

ホゾ接ぎの補強処置
ほぞ接ぎ部は、補強としてビスで固定しています。(通常、ほぞ接ぎではビスは使いません。)
ビス止めしてホゾ接ぎを補強

ほぞ加工の為、一部解体していた板を復旧して完成
ぱっと見た感じではホゾ接ぎの場所は目立たない仕上がりになっています。しかし、あくまで応急処置でありますので、今後様子を見ながらフェンスの維持管理を行っていきます。
復旧したウッドフェンス

まとめ
5年もてば良いほうかと思って作ったウッドフェンスでしたが、2013年に製作してからちょうど7年となります。当時、ウッドフェンスの制作にあたり心配だったのが、木材の腐食と台風に耐える強度を確保できるのかということでした。
これまで、塗料のメンテナンスとして、夏の日差しを受けて塗料が傷んだウッドフェンスに、毎年防触塗料を重ね塗りしてきました。それから、ウッドフェンスは隣家の日影に入ることが幸いして、これまで直射日光をあまり受けなかったことも長持ちした要因かと思われます。
今回はウッドフェンスを製作してから初めての修理となりますが、当時の端材が残っていたこともあり、端材を活用したDIYを行うことにしました。もしも根接ぎを参考にしたフェンス支柱の修理をDIYで行う際は部分解体してから接ぎ作業を行うことをおススメします。
それから、ウッドフェンスの立地条件によりますが、風を強く受ける場合は支柱の部分的な修理ではなく、支柱の交換をおススメします。簡単な記事ではありますが「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントなりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
| プロモーション |